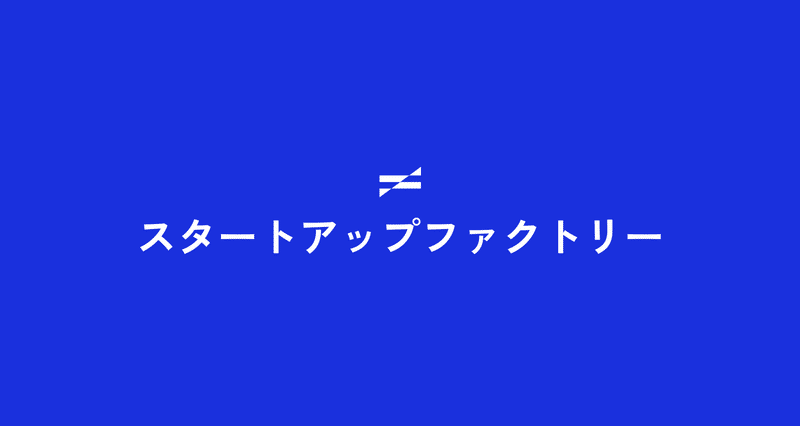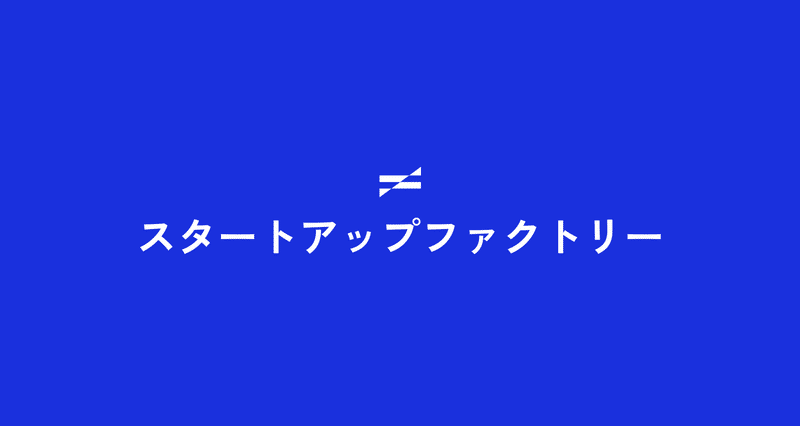【監修】ものづくりスタートアップのための契約ガイドライン&フォーマット
本ガイドラインのねらいものづくり系スタートアップが新しいアイデアを実際のプロダクトにし、市場へローンチしていくためには、ものづくりを担う設計・製造業者等との協業が欠かせません。
しかし現状では、スタートアップと設計・製造業者等の間の取引において、お互いの認識のギャップ等が原因で少なからずトラブルが発生しており、そのすり合わせのプロセスである”契約”のノウハウ普及が不可欠となっています。
このような背景から、本ガイドラインは、多くのスタートアップ、設計・製造業者、支援プラッ